SES(システムエンジニアリングサービス)企業から自社開発企業に転職して2年が経ちました。
今回は、私が実際に感じた5つの大きな違いを、リアルな視点でお届けします!
- これから転職を考えている方
- SESで働いていて将来が不安な方
- 自社開発との違いが気になる方
には、きっと参考になるはずです。
それでは早速紹介していきます!
違い①:技術選定に関われるかどうか

SES:技術スタックはアサイン時点で決まっている
SESでは基本的に「決められた技術」に従う形が多く、プロジェクトに入る時点で技術スタックはほぼ固定されています。
私はVanilla.jsとSQLを使用するローコードエンジニアリングのプロジェクトへのアサインだったため、モダン開発の経験やフレームワークを体系的に利用する機会を得ることができませんでした。
自社開発:新しい技術の導入に携わるチャンスあり
自社開発では、新しい技術の導入や改善提案に関わるチャンスがあるのが大きな違いです。
チームで「どの技術が最適か?」を話し合う文化があり、エンジニアとしての視野が広がります。
実際、いまの会社ではもともとJavaScriptで書いていたコードをTypeScript化する動きがあったり、分析ツールなどの導入を社員で検討・導入されています。
違い②:業務の幅と責任感

SES:基本的には仕様書がある
仕様書通りに実装する「受け身の業務」が多く、設計や上流工程に関われる機会が少ないことがあります。
反対に上司がITに詳しくなく、全てを丸投げされるケースもあります。
私がアサインされたプロジェクトは後者で、要件のヒアリングから仕様を考えて提案することまでこちらがすることが多々ありました。
自社開発:当事者となり仕様から決めていく
企画〜設計〜開発〜運用まで、幅広い工程に携わることができ、プロダクトへの当事者意識が自然と芽生えます。
違い③:学びの深さと継続性

SES:プロジェクトによるが、高いスキルが入らないことも
案件が終わるとチームも解散になります。
プロジェクトごとに扱う技術が変わるため、深く腰を据えて学ぶ時間が取りにくい傾向がありました。
私の場合、1つのプロジェクトを継続する形でしたが、ローコード開発のプロジェクトでした。
ローコード開発の現場では、コードとして書けるのはfor文やSQLのセレクト文など、エンジニアとしては少し物足りないものでした。
もちろんローコード開発のプラットフォームの学習はしましたが、案件が変わればこのプラットフォームの開発ではないことが考えられます。というか、だいたいそうです。
そうなると、勉強にもあまり身が入りませんでした。
自社開発:社内での情報交換などもある
同じプロダクトを長期的に育てていくことになるため、技術の深掘りや改善のサイクルが回しやすいと感じます。
社内でのLT会などがおこなわれ、社内での情報交換もあります。
違い④:チームとの一体感

SES:少人数の場合は肩身が狭いことも
基本的に客先常駐が多く、チームメンバーの入れ替わりが頻繁になることもあります。
孤独を感じることもありました。
ただ、社内の面倒な仕事(書類作成や申請など)は社内の方がしてくれたので、技術派遣メンバーは技術に特化した仕事に注力できたことはよかったです。
自社開発:「仲間意識」が高まる
「同じプロダクトを育てる仲間」として、共通のゴールを共有できるため、チームに一体感が生まれやすいです。
違い⑤:将来のキャリアへのつながり

SES:理想のキャリアに向けてのコントロールがしにくい
どの案件にアサインされるかは会社次第で、キャリアの積み上げが見えづらいことがあると感じました。
同じ現場にアサインされた先輩は、VR開発の知識や経験を持っていたのに、IoT開発の現場に入っていました。
1つのスキルに特化して伸ばしていくことが難しい形だと思います。
一方で、自分のキャリアの方向性が固まっていない人にとっては、SESでさまざまなタイプの案件にアサインされてみるのも良い経験になると感じました。
さまざまな経験を積むことで、向いていることや向いていないことが明確になってくると思います。
私も実際に技術派遣で働いてみて、「自社プロダクトを育てる」ことに興味を持つようになったよ〜
自社開発:裁量が頑張り次第でどんどんアップしていく
プロダクトを成長させたり、事業をスケールさせる経験を積んだりする中で、PM、テックリード、PdMなどへの道が拓けやすいと感じています。
また、自社開発企業の中でも私のいる会社は創業5年目くらいのスタートアップということもあり、どんどん会社の規模も成長しています。
そのような環境だと上のポジション数も必然的に多くなっていくため、上の役職や職務を目指す人にはおすすめです。
違い⑥:評価制度

SES:「評価する人」に成果が伝わりづらい
SES時代は、評価基準が現場ではなく「営業」や「契約単価」に依存する部分が大きく、どれだけ頑張っても評価に反映されづらいと感じていました。
現場のクライアントからの信頼を得ても、会社側が細かく把握していないことも多かったです。
評価制度は、私の前職では実質関係ないような実態でした。
1年目から2年目になるとき、評価面談などは特になく、2年目に給与明細を見たら基本給が5000円だけ上がっていたのが印象的でした。
自社開発:「評価する人」と同じチームで働けるため成果が伝わりやすい
一方自社開発では、チームの成果やコードレビュー、プロジェクトへの貢献度が明確に評価に反映されるようになり、やりがいを感じやすくなりました。
定期的な1on1や個人で立てた目標の達成度合い、チームや会社への貢献度など、エンジニアとしての成長をきちんと見てくれる環境は大きな違いでした。
違い⑦:収入面の違い

SES:なかなか給与アップが難しい
SES時代は、案件の単価と自分の給与のギャップにモヤモヤしていました。
どれだけ高単価な現場に入っても、昇給は微々たるもので、年収も300万円台〜400万円台で頭打ちという印象でした。
新卒でSESに入って数年間というタイミングだったこともあり基本給も低かったため、2年目、3年目になったときに昇給額よりも税負担額の方がプラスになり、手取りはマイナスになってしまいました。
当時はかなり生活が厳しく、毎日お金のことを考えていました。
コロナ禍で飲み会とか少なくて、正直助かった、、、、
自社開発:頑張り次第でどんどん給与アップ
自社開発に転職してからは、基本給が上がっただけでなく、業績やスキルアップに応じた昇給制度が整っている環境になりました。
実際に、転職した後の2年間の昇給で、年収も150万円以上アップしました(ボーナス、基本給ともにアップ)。
成果が収入に直結する仕組みは、モチベーションにもつながっています。
マイナスなところとしては、見込み残業がある会社も多いことかな。
まとめ:転職して良かったこと
SESにも学びはもちろんありましたが、私の場合、自社開発に来てからは
- 技術的な裁量
- キャリアの見通し
- 開発する楽しさ
がぐっと広がりました。
自社開発が正解というわけではありませんが、「プロダクトを自分の手で育てたい」と考える人には、ぜひおすすめしたい働き方です。
関連記事
-
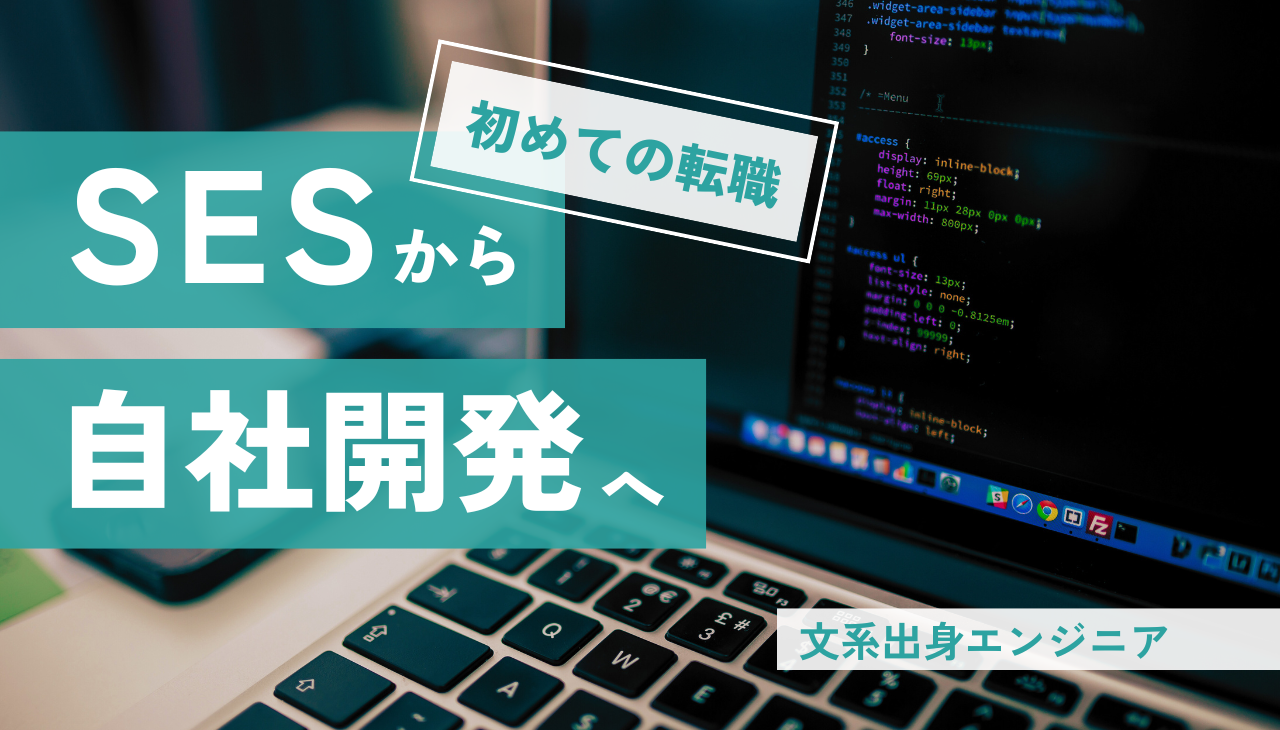
-
文系出身エンジニアがSES企業から自社開発エンジニアへ転職した記録【実体験】
SESで3年働いた後にWebエンジニアへ転職した私が、どのような流れで転職活動を進めたのかをまとめました。Web開発の経験がなくても何とかなった!!
-

-
文系学部卒がITエンジニアを目指しIT業界へ就職した方法
文系出身だとITエンジニアを目指すのは厳しいのでは、、、そう思っていませんか。文系出身者の強みもたくさんあるので諦めないで!

